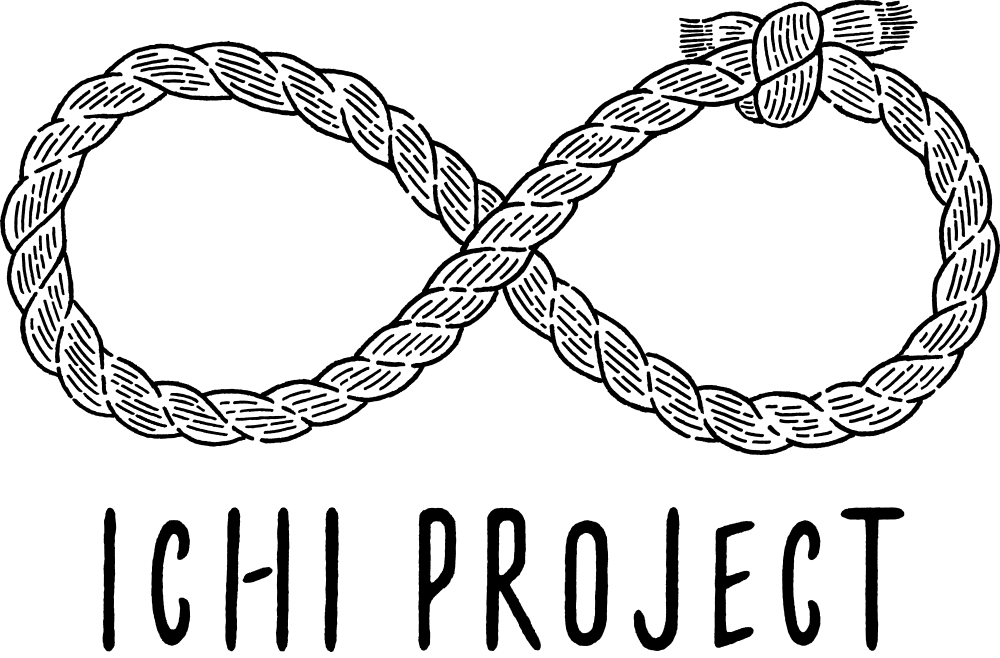{ モノ・ローグ }
- 「畏敬と工芸」展示解説=それぞれのモノがたり[その3]
- 市プロジェクト・ウィークエンド[第2期]:「畏敬と工芸」の展示で、キャプション代わりに作成した展示解説書。参加者が半年かけてリサーチしてきた「工芸」と「観る人」とを結ぶレポートを、「それぞれのモノがたり」として編み上げました。

ぜんまい織り:齋藤則子
日本のテキスタイルには、北から南と各地の特徴がより濃く表現されているものが多い。私が今回テーマとして選んだ「ぜんまい織り」もそのひとつである。織物に使用される糸の種類には動物繊維の絹や植物繊維の綿、苧麻、芭蕉など様々な種類が存在する。東北の気候は雨・雪が多い。綿花が育ちにくい環境であるため、それに代わる木の皮や植物が織物の材料として使われたと考えられる。
山や川、野と共存し生活してきた東北の人々は、生きていくために自然から命をいただき食し、自然からその身の一部を分けていただき衣として、厳しい気候から我が身を守ってきたのではと思った。その中でもぜんまい織りは、雪解けを待って耐え忍びようやく春先に芽吹くぜんまいの綿毛を使用する。雪の中で新芽を守るようにぜんまいを覆っている綿毛を使用するのは、それを纏う者も力強く健康であるようにという願いを込めてのことだと考えられる。
ぜんまいは5月頃、山の中の水辺の多いところに生えてくる山菜で、くるくると螺旋状になった先の芽のあたりが茶色い綿毛で覆われている。
私が生まれ育ったのは月山の麓の西川町というところで、県内でも雪深い場所である。1年の半分は冬だと感じるくらい静かで寒いため、春が非常に待ち遠しく楽しみに感じられる。私の父は山菜取りが第二の仕事であるかのように毎日山に入り、春はたらの芽、ウド、ワラビ、ぜんまいを、秋にはいろんな種類のキノコや山葡萄などを採ってくる。祖父母が健在だった小学生の頃、父が山から帰ると庭に大きな御座を広げて家族みんなで座り、父が採ってきたぜんまいの綿毛を取ったり、細筍の皮を剥いたり、山葡萄の実を大きなビニール袋に入れて足で踏んでつぶしたりした。当時は当たり前のように思っていたが、今思えばたくさんの山の恵みをいただき、口にするまでの過程においては、家族のコミュニケーションの場もいただいていたのだと思った。
父はよくぜんまいを採ってきたが、芽のまわりの綿毛は全て取って捨ててしまっていた。まさかあの茶色い綿毛が糸になり、布になり、作品になっていくなど、当時の私には想像もできなかったと思う。
今回このテーマを取り上げるにあたり、以前から気になっていた米沢にある「原始布・古代織参考館 出羽の織座 米澤民藝館」に何度か足を運んだ。民藝館ではぜんまい織りをはじめ、榀布、からむし布、麻布、葛布、蕁麻布などの日本原始布、古代織物の復元と存続に取り組まれている。昔織り蔵として使用していた蔵を移築したという建物はとても趣きがあり、展示されている数多くの原始布や作品を眺めていると、古代の人々の生活に引きこまれていくようだった。原始布以外にも、古代刺子や様々な編具、弥生機、腰機など数多くの参考資料や文献があり、訪問すると館長の山村氏がわかりやすく説明してくれるので、どんどん興味が深まっていった。山形を訪れた際は是非お立ち寄りいただきたい場所のひとつだ。
ぜんまい織りの緯糸をつくるのには半年以上の時間と工程が必要だ。ひとつのぜんまいから採れる綿毛はとても少なく、織物に使用するにはたくさんの綿毛が必要であり、また糸にするまでの工程が非常に難しい。
機能面では、防虫・防カビ、保温性や防水性に富んでおり、他の材料では感じられないくらいしっとりとしている。ストールなどは体にとても馴染んで纏いやすい。初めて作品に触れた時、これがあの野山に生えているぜんまいかと、くるくるとした芽を覆っている茶色の綿毛を思い出した。山からいただいた恵みを捨てるところなく活用していた昔の人々は、今私が感じている以上に、自然に対し畏敬の念を感じていたに違いないと思った。
その織布は柔らかく、とても素朴で独特な自然色をしている。他の織物で見られるような煌びやかさはないが自然のパワーを感じられる。また私にとっては家族や幼い頃を思い出させてくれるあたたかいものなのである。

笹野彫:鈴木伸夫
米沢の古書店で「よねざわ豆本」という古いシリーズを見つけた。「これは何の図柄だろう?」と、表紙に惹かれ手に取った一冊が『笹野の里(笹野彫)』という豆本だった。「笹野彫」といえば、米沢藩主上杉鷹山公が、農閑期の副業に奨励したことで興された「お鷹ぽっぽ」が有名だ。魔除けや縁起物として親しまれ、山形の家庭では床の間や茶箪笥に置かれている光景をいまも目にするが、その豆本には「笹野彫」のほかに、昭和40年代の当地の習俗や風景が写真とともに記されてあり、その質朴さに引き込まれた私は、実際に笹野を歩いてみたくなった。
毎年1月17日に行われるという、地元の「笹野観音」例祭にむけて、一刀彫の職人たちがせわしく手をうごかしている。里人がアブラコと呼ぶ喬木がみるみる花の形になっていくさまを見て感嘆の声を抑えきれない。春の彼岸に生花がなかった時代のなごりもあってか、地元では流通が発達した現在でも、ケヅリ花を彼岸花として仏前にあげないと先祖にすまない気がすると、例祭の時期に色とりどりの「花」を買い求め仏前に飾るのだという。それが、笹野彫のルーツであり、アイヌ民族の〝削り掛けの技〟を伝承するといわれる「笹野花(ケヅリ花)」だった。
かつて当地周辺に居住していたアイヌ民族は、東方征伐によって北方に追いやられたが、この笹野花を見ていると、アイヌの儀礼具「イナウ(木幣)」や「ヘペライ(花矢)」にも似た、削り掛けの技が色濃く残っているとうかがえる。また、大胆に刃を入れる一刀彫には、アイヌの木彫り人形と、笹野彫のもうひとつのルーツといわれる西日本由来の御守「蘇民将来」、どちらにも共通するものが見受けられる。さらには、お鷹ぽっぽの〝ぽっぽ〟とは、アイヌ語で〝玩具〟を意味するとのことで、昔は独楽やこけしといった木地玩具のようにカラフルだったというから、信仰玩具ともみてとれる。笹野彫は、自然や先祖への感謝や祈りと、多 様な由縁の技が融合してひとつの形に落とし込まれた〝ミクスチャー工芸〟のようにも感じるのだ。
豪雪地である笹野の春は遅く、ひと昔前までは、春の彼岸というのにまだまだ雪深く、場所によってはまったく自分の家の墓が見えないから、適当に見当をつけて花をさし、ぼたもちをあげて帰って来ていたという。墓参りの人が絶えて静まりかえった墓地に、色とりどりのケヅリ花や紙花が、白い雪の斜面に冴えて残る。本家に一族郎党が集まり酒をくみかわし、子供達はぼたもちのあんこやごまを口にくっつけて笑ってざわめいている光景が、いまもどこかで見られるのだろうか…。
笹野花が感興のきっかけとなり、日本に広く分布する(した)といわれる「削り掛け」の習俗を調べはじめたわけだが、ここ数年でひっそりと削り掛け文化が消滅してしまった地域の多さ、いま在るつくり手の少なさに愕然としている。様々な情報が瞬時に手に入れられる時代だが、現在にまでこの削り掛けの文化が生きているところがどれだけあるか、またどのような人がこの技を受 け継いできたのかについては、実際に足で見聞しなければなかなか掴めてこないのだ。時流のなかで廃れてしまっていることにふと世間が着目したときには、その技は消えてしまっていたり、商業的なニーズを優先してしまっているうちに本来の姿が消えてしまっていることも多いかもしれない。モノが、そのモノの形をしている由縁を辿っていくうちに、山形に生まれ育った自分のルーツを工芸から垣間見れたことは幸運であったし、いまがそのギリギリの時代かもしれないというのが率直な思いだ。花のない冬に、工芸によって季節を彩り、四季を感じ取れる笹野花のような、朴訥な農村の美意識を忘れたくないものである。そして、この文を書いているいまもまた、新しい情報を手掛かりに、地方のある博物館に電話を入れている次第。「削り掛け」を軸に、いまに生きる「畏敬と工芸」を探しに、暇をつくっては少しずつ旅に出てみようと思っている。

俵:杉山ひかる
俵は食用の米を入れるためのものと思われがちだが、種籾(たねもみ)の貯蔵のために用いられたのが始まりであるとされている。種籾とは、種として苗代に蒔く目的で選んでとっておく籾のこと。発芽を促す際、俵ごと水に浸して木の棒などで抑えておくと、米がバラバラに浮いたりせず定着しやすくなり、鳥についばまれることもなくなるという。20日ほど水に浸して取り上げ俵を開き、2〜3日して籾の割れ目から芽が生えたら田んぼに植える、というのがかつての主流であった。
古くから米と共に生きてきた日本人にとって、米は生きる糧であり信仰の対象でもあった。現在でも、「田の神」「稲荷神」といった、米にまつわる神信仰が全国各地で見られる。稲の生命力が宿る種籾は、田の神が宿る「依り代」のように考えられており、石川県能登半島で伝承されている「アエノコト」と呼ばれる儀礼では、籾俵を祭祀対象とする事例もある。
種籾は次の年の稲作を左右する重要なものであるため、とりわけ大切に保管された。俵を保管する際は、鼠害を防ぐために杉の枯れ葉などを絡めたり、梁から縄で吊るしたりする手法を取っていたようだ。この、俵が吊るされる独特な光景は、江戸時代頃の女性の出産の風習に重ねて見ることができる。昔の出産は天井から「力綱」と呼ばれる綱を吊るして、それを握って縋りながら出産するか、もしくは枕状に高く積んだ俵、または藁枕に寄りかかって出産していたとされている。横伏せで出産すると難産になると信じられていたのだ。また、出産後も横になるのはよくないこととされ、数日間綱に縋り付いて座っているような状態であったようである。
籾俵は言わば「生命の源の象徴」であり、籾俵が吊るされる様になぞらえて妊婦が縋り付いて出産をする様子からは、新しい命の誕生に対する強い念が感じられる。新生児が無事生まれる確率が今とは比較できないほど低い状況にあった昔は、文字通り神に縋るような思いで出産をしていたのではないだろうか。また、俵(タハラ)は、お腹のハラという言葉が由来となっているという説もある。
私の家は祖母から米を貰っていたので、米を買ったことはほとんどなく、米に困ったこともない。それでも米一粒には七人の神様がいると教えられ、一粒も残さずに食べるようにと厳しく言われてきた。それには、かつての先人たちが命をつないで残してくれた物に対しての、感謝の意が込められている。私たちが受け継いだ、米やそれに伴う風習、そして私たち自身の命を、これからも大切にしていかなければならない。

山の神人形:田村岳男
展示の人形は、「山の神」の御神像です。山の神は、里の民にとっては田畑の神であり、木樵や炭焼など山の民にとっては山を守護する神で、禁秘に厳しい女性の神です。
この山の神を祀る「山の神勧進」は、山形の最上地方で今なお行われる行事で、春や冬の日、年若い男子が、森に囲まれた山の神社に大切に祀られているこの神像を大事に手にかかえ、「ヤマノカミノカンジン」と呼びながら集落の家々を巡り、お供えのお菓子や米や賽銭を集め、お祀りする行事です。参加が許されるのは15歳以下の男子のみで、前の晩から神社や宿に籠り、明くる日集落で勧進を行い、御神像を神社へお戻しして終了します。集落では、男の子が生まれると、生まれた家や厄年のひとがこの人形を自らつくって奉納するとされており、集落の山の神神社には、展示のような御神像が数えきれないほどおさめられています。
山の神の御姿は、何年も何年も子どもたちの手に抱えられ、おんぶされて、木もボロボロ、角がすり減っておりますが、これこそ、生まれて死ぬまで山と一体の村人の手がつくった形、その山と人間の関係のあかしのように私には思えます。そんな自然と人間の密接なつながりに惹かれ、真室川から山形のとんがりビルへ来ていただきました。
山形県は山々に囲まれ、くっきりした四季の移ろいがあります。その移ろいは、頬をつたう汗、しばれて凍える手というように、否応なく、自分のからだを意識させます。そして、山や自然、その彼方の神でさえ、観念よりからだで知り、自然への畏れを皮膚で感じる感性を、山形のひとのからだに刻んでいきました。その刻まれたからだの記憶が、修験から伝統工芸、農や食において、山形のひとに今でも息づいていると私には思われてなりません。
ぜひ、足を止めて、目の前の優しいお顔の人形と対話してください。そして、山形に生まれた方なら、自分の皮膚に今でも息づく山や自然の記憶と畏まる思いを感じていただければ、たいへんうれしく思います。

羽黒鏡:野田晶子
昔、沼や池に鏡を投じる風習があったという。鏡と池はモノの姿を映す作用が同じで、水面が鏡のように見られるところから、一般にそれらの池は、鏡ヶ池と呼ばれている。
なぜそういった風習があったのか。人間には、水や鏡の「全てを映す」作用に対して、驚きと畏れの観念があり、そこに一種の霊力の潜在を感じたと考えられている。例えば、山の中の静かな池のそばを通る人の影が水面に映るやいなや、池がその人を水中に引き込んでしまうという伝説や、写真が登場したばかりのころ、顔や姿が映されれば魂まで抜き取られると、写真に撮られることを嫌った風習などからも理解ができる。基本的には、このようなことから池や沼への崇拝が生まれ、当時貴重だった鏡を水中に奉納する習俗が生まれたと考えられている。
また一方では、鏡には人の心が乗り移るという。この点から、自分の顔や姿を映した鏡を身代わりとして池に投じることで、より神に近づこうとした信仰なども考えられる。
鏡ヶ池は、全国に数多く確認されている。中でも代表的な鏡ヶ池が、山形県羽黒山の出羽三山神社境内にある。羽黒山は、月山、湯殿山とともに出羽三山と呼ばれ、大和の大峯、紀州の熊野とともに日本三大霊場と言われる山の一つだ。そこから出土した鏡は「羽黒鏡」と呼ばれている。羽黒山がある鶴岡市の名物お菓子、木村屋「古鏡(こきょう)」の元となった鏡だ。奇遇にもそこの神社で、池中納鏡参拝を現代に蘇らせた「いけのみたま心願参り」をやっているという情報を入手し、実際に体験してみることにした。
さまざまな参拝プランの中から私が選んだのは、山伏案内と鏡ヶ池への納鏡のみのシンプルなコース。参拝料2000円と引き換えに、500円玉サイズの納鏡用鏡、願いごとを書く紙、プレゼントのおまもりを受け取った。受付と同時に、お店のお母さんが神社に電話を入れる。あれこれ考え願いごとを書いていると、案内役の山伏の方が現れた。挨拶が済むと、彼はほら貝を吹いた。低音と高音を繰り返す力強い音色には、魔除けやお清めの意味が込められているという。
聖徳太子の従兄弟にあたる出羽三山の開祖、蜂子皇子のお墓など、いくつかのスポットを案内していただきながら歩を進めると、大きな大きな茅葺き屋根が見えてきた。冬の間登拝できない月山、湯殿山の神様とともに祀った神殿「三神合祭殿(さんじんごうさいでん)」だ。高さ28m、厚さ2・1mの茅葺屋根は、日本最大だという。
そして、その神殿の前に、目当ての鏡ヶ池が広がっていた。池の中に多数の植物が生え、〝鏡ヶ池〟とは程遠い印象。その植物は近年自生したもので、取っても取っても生えてきて困っているそうだ。
神殿と鏡ヶ池が正面に見える塀の中に通される。そこには、1mほどの丸い石をくり抜いてつくられた、小さな鏡ヶ池があった。そこで鏡ヶ池についてのお話を聞く。驚くことに羽黒山のご神体は、池そのものなのだ。羽黒神が姿を現す池として信仰されてきたそう。昔は、羽黒神社と書いて「いけのみたま」とお読みしていたという。その池に、人々は貴重な銅鏡に願いを託し、納めたと考えられていたそうだ。
話が終わり、ついに鏡と願いごとを書いた紙を池に投じるときがやってきた。改めて願いごとを読み返し、鏡とともにそっと池に投じた。瞬く間に沈んでいった鏡に驚きつつ、じんわりふやけていく願いごとを見守りながら二礼二拍手一礼。このとき私は、9月の富士登山のことを思い出していた。
職場の先輩に誘ってもらえて、偶然行けた。人生二度目の登山にして、日本最高峰。朝7時頃富士五合目吉田口に到着し、1時間程身体を慣らしてから登山開始。休憩をはさみつつ約10時間、ゆっくりと小さな歩幅で、山を登り続けた。途中何度も挫けそうになりながらも、なんとか頂上に到着。山小屋まで歩いていく途中に、鳥居と賽銭箱がぽつんと置いてある神社らしきものがあった。頂上にたどり着いた証を残したい。そんな気持ちから、私はそこに賽銭を入れて、お参りをした。その行為が、昔の人が羽黒山に出向き、鏡を投じたことと重なった。ようやくたどり着いた憧れの場所に、分身を納める。私は富士山に登ったことを思い出すと、なんだか心強くなる。そういった感覚を1000年以上も前の人々も持っていたのか。そう思うと、とても不思議な気持ちになった。また、平安時代からの日本人が納めていたのは、お金ではなく鏡。古来の美意識を感じ、嬉しくなった。
羽黒鏡から富士山、平安とつながった心の旅。決して会うことの出来ない祖先たちに思いを馳せ、通い合うような感覚が持てたことが嬉しかった。

箒(ほうき):土屋理奈
箒はもともと朝廷の神事における「ハレの道具」として、奈良時代にはケガレを清める宗教儀式に使われていました。そのあと宮中で一年の煤を掃う行事、煤払い(すすはらい)が定着し、そこから10世紀にはじめて「掃除」という概念が生まれ、それまで「ハレの道具」だった箒が、「ケの道具」として日常で使う道具になりました。鎌倉時代には、掃除という行為自体が仏教の修行の一部として位置付けられていました。その時代背景には、飢饉や疫病が流行っていたことがあげられます。ケガレこそが日常に影響を与えると信じられていたことから、信仰を通して災いを掃き清めるという役割に期待が込められていたのではないかと考えられています。
日本では、掃除という行為に心を清めるという意味も込められてきました。心も含めて、悪いものから身を守るという幅広い意味があるのだと思います。一般的に掃除とは何らかのケガレを取り除くこと、払いのけることですが、それはケガレを取って〝ハレ〟の状態をつくるために行うとともに、〝ケ〟の状態(= 日常の平穏)を保つために行うのだと考えられます。そして日常の掃除は、暮らしの場を整えるためのものであり、祭りや行事にともなう掃除は何らかの神を迎える準備と言えます。さらに、日本をはじめとするアジアの仏教国では、伝統的に児童や生徒による学びの場の掃除が行われています。我が国のその伝統は江戸時代の寺子屋や、寺院教育にまで遡ります。
掃除は悟りを開く手段であり、人間修行や心を磨く重要な方法を成すものだという仏教的掃除観があることがわかります。
それから、箒には、箒神と言われる神が宿っていてそれは産神(うぶがみ)とも言われています。掃く・はき出すという行為が出産と結びついて、妊婦のお腹を新しい箒で撫でると安産になると言われているのです。また、箒を玄関に逆さに立てることで、長居の客をはき出すというおまじないもあるそうです。掃除だけではなく、日本ではいろいろな意味があるのが面白いです。
地域によって使われている箒の素材はいろいろで、ホウキ木、棕櫚、藁、枝などがあります。種類も、草箒、棕櫚箒、竹箒など、用途によって使い分けられています。今回展示させていただいた箒で山形のものは、山形市尾島ほうき店さんの座敷箒、庄内町槇島地区で200年もの伝統があり、種から育てるところからつくられた槇島ほうき、庄内地区小関地区で伝承されている由右エ門ほうきで、職 人さんや地区の人が一つひとつ手づくりされているものです。現代は強力な吸引力の掃除機やお掃除ロボットなど、掃除道具もとても便利になっていますが、箒で掃くという一見不便に見える動作の中に、新しい価値観や人間と自然との関わりなど、心に作用する何かを感じてもらえたらなと思います。神具からはじまった箒は、使われ方を変えながらも常に生活の傍にあったことがわかり、私自身見方が変わりました。つい先日、地域の奉仕活動で、遊歩道の赤く染まった桜の落ち葉を竹ぼうきで掃きました。早朝に軽い労働をし、きれいになった道を見ると、やはり清々しい気持ちになります。辿ってきた背景を思いながら、これからも箒を使っていきたいと思います。

鈴:渡部萌
人の日常がより自然と密接だったとき、人はどのように世界を捉えていたのか。私は近ごろそういう興味があり、そんな視点から畏敬と工芸について考えてみました。
自然は人の生きる術であると同時に、人に死をももたらすものです。人は自然界から生きる糧を得ますが、生と死が複雑に絡み合う自然に立ち入るということは、同時に死に身をさらすことでもあります。人と自然界、生と死、日常と異界、自分と他人、等々、そこに緩やかな境界を示すことで混沌とした自然界と距離をとり、人は人として安全な暮らしを確保してきたように思います。そして物や慣習、儀式、言葉などは、こちら側と向こう側の境目の目印なのではないかと思うのです。
境目というのはとても興味深く感じます。畏敬と工芸というのはまさに、人と自然の間に、人から自然に向けてつくられたものを指すようにも思えます。境目を示すものとして、音はどうでしょう。鈴や笛、太鼓などの音の鳴るものは古くから人の精神に関わるものでした。日本では古く縄文時代に土の鈴がつくられて、古墳時代には金属製の鈴が出現しています。鈴は、木の実やマメを振ると種子が動いて鳴ることを真似てつくられたといいます。木の実やマメの種子が殻や鞘と一体でないのに、外殻とともに成長する様は人に神秘を感じさせたそうです。
鈴の音には獣や邪気を払うと同時に、神を引き寄せ身を守る力があるとされ祭事から日常まで様々に用いられてきました。寺のお堂の軒の四方に風鐸と呼ばれるものが吊り下げられています。これは青銅でできていて、強い風が吹くとカランカランと鈍い音がします。強い風は流行病や悪い神を運んでくると考えられていたことから、邪気除けの意味でつけられており、音の聞こえる範囲は聖域で災いが起こらないとされていました。その後風鐸は暑くて病の広がりやすい時期の魔除けの道具、暑気払いの器具として定着していき、風鈴の形になるそうです。
私はたまに熊鈴を下げて山に入ります。そのときに鈴の音は、木々や草の生い茂るその空間に対して私の存在を示し、私のいる範囲に予期せぬ事態が入り込まないように機能していると感じます。物陰に潜む獣か一瞬先の未来か、鈴の音は空間に広がりまだ見ぬものに対して働きかけます。様々に線引きされ確保された安全地帯から出たとき、人はいま目で見ている以外の世界の可能性に対して敏感になるような気がします。
死をもはらんだ自然の大きな力や、理解のできなさを強く感じながらも、そこに生きる方向を見出している様が、畏敬ではないかと思います。言葉や説明で生活が形成されている現代では、その外にある畏敬という感覚は機能していないのかもしれません。かつて境目につくられた様々なものは、逆に私たちに対して人と自然の密接さや当時の人のまなざしを示しているようです。
会場に展示している鈴・鐘はS-1馬鈴を除き、鳴らしていただけます。丁寧にお取り扱いください。なんとなくその音の先を捉えるイメージをしてもらえたらいいと思います。