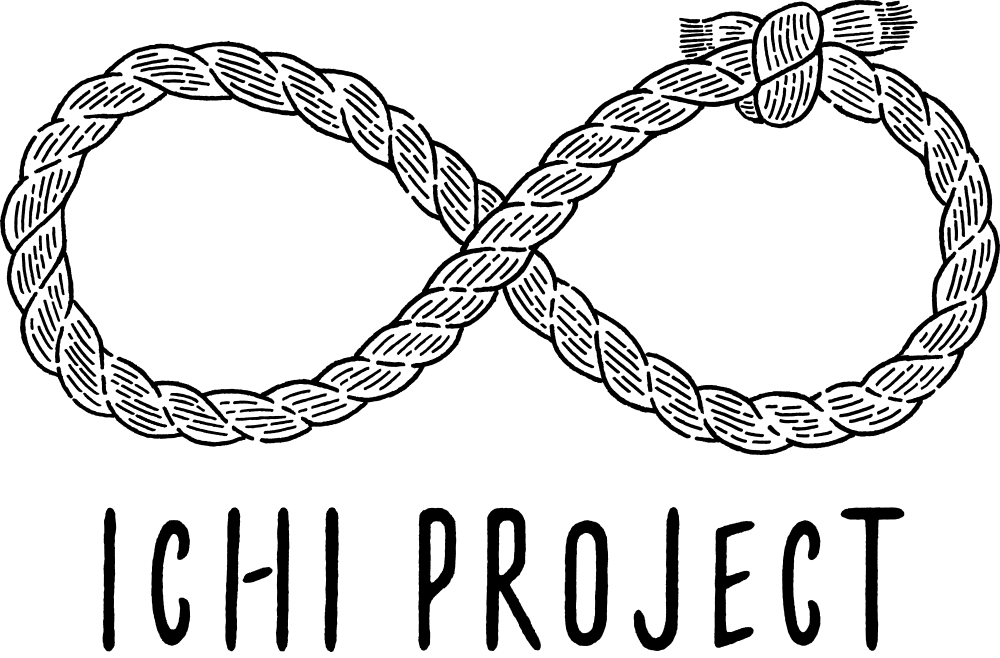{ モノ・ローグ }
- 「畏敬と工芸」展示解説=それぞれのモノがたり[その2]
- 市プロジェクト・ウィークエンド[第2期]:「畏敬と工芸」の展示で、キャプション代わりに作成した展示解説書。参加者が半年かけてリサーチしてきた「工芸」と「観る人」とを結ぶレポートを、「それぞれのモノがたり」として編み上げました。
釦(ぼたん):大江よう
人類が着用してきた衣服の長い歴史のなかで、その多くはスポッと被る貫頭衣などと呼ばれる種類や、前後または左右を紐などで結ぶ着物のような形態が大半をしめていました。「釦で前を留める」という機能が発達したのは、ここ千年ぐらいだと言われています。
もともと、目・口・耳など、自分と外を隔てている境界線から悪霊が侵入しやすく、それを妨げるために目や口元への化粧、耳元などの装飾が呪術的に行われてきたとされています。それは衣服においても同様で、首・背中・袖・裾口などあいている部分から悪い要素が入り込んでくると長く信じられてきました。それらを防ぐための刺繍やビーズ、ステッチや染色などによる装飾が受け継がれ、各地域の衣装や文化として残っているようです。
装飾に用いられたのは、海でとれる貝や魚の骨、山でとれる獣から得られる骨や牙、皮など、身近なところで手に入る生命力のある素材でした。特に貝は、生命力・生殖器の象徴。そういったものを装飾として、丸く小さく切って、境界線の装飾に用います。結界のような美しいパターンにしたり、重ねて音が鳴るようにしたり、釦という「留める」機能の前に、そうした装飾的な使われ方がありました。
現代を生きる自分たちの日常の中でも、例えばプラスチックではなく、ちゃんとした貝のボタンに付け替えてみる、装飾的に多くボタンを付けてみるなど、そういう行為によって、忘れられていた釦の精神性・畏敬を取り戻すことができるのではないかと思います。

水引(みずひき):沖津直美
私たちが大切な人へ贈り物をするときや、神様へのお供え物によく目にする水引。赤や白、金色や銀色など様々な色で、いろんな美しい形をした結びがあります。細い紐から生まれる美しい形には心があたたかくなるものがあります。水引の歴史を紐解くと、飛鳥時代に中国から日本の宮廷への贈り物に麻の紐が結ばれていたことがはじまりとの説があります。
水引は神聖なものとされ、厄除けや魔除けの意味があることから、相手と清らかな関係を築き続けたいという願いが込められていたのではと感じます。そもそも古代から万物に神が宿るという考えがあり、結び目までにも神の心や力が宿っていると考えられてきたようです。(その力を産霊(ムスヒ)と呼ぶ。結びの語源と言われている)。行事やマツリゴトが日本で行われる時代になると、四季を表すような色とりどりの水引が生まれ、素材も和紙の紙縒や絹糸を巻き付ける鮮やかなものになっていきました。結びの形の歴史や意味も面白く、代表的な「本結び」は歴史が古く、古代ローマ時代には子孫繁栄を願って腰に結んだり、治りが早くなるよう願いを込め包帯を結ぶときに使われていたようです。「あわじ結び」は、「アワ」という言葉自体、天と地を表す言霊とされ、天と地、神と人を結ぶものだという説があります。これらの結びは、戦前には女学校では習い事の一つとされ、ただ結ぶだけではなく、人と人、心と心を結ぶという意味も込めながら、礼儀の一つとして根付いていったようです。現代では簡易的に水引の絵が印字されている熨し付きの紙や、すでに結ばれている水引が付いた御祝儀袋を見かけたり、私自身も使っていたので、水引の結びが誰でも出来ることや、魔除けになるとは知らず、驚きと関心の気持ちが生まれたのでした。
山形市に創業100年を誇る、佐藤紙店祝儀堂という代々水引を結んでいるお店があります。お店の歴史や、水引の歴史を三代目の奥様にお聞きすることができました。この度の展示品は奥様のお話も参考にさせていただき、調査を踏まえ、自分で水引を結ぶことに挑戦しました。材料も大麻を使うことにこだわって単色に揃え、古代の風合いをも感じさせるものとなっています。

獅子幕(ししまく):菊池芙生子
獅子舞はもともと、仏教から派生した布教活動の一種で、〝獅子〟は麒麟やバクや龍を具現化した架空の獣である。目に見えぬ自然への畏れなどマイナスの感情を仏教への信仰(=獅子の存在)というプラスのイメージへ発展させたものだ。
獅子舞をはじめ、念仏踊りや田植え踊りなどの地域に伝わる農村文化は山岳信仰とも深い結びつきがある。最上義光公が伝統芸能を推奨していたため、山形には多数の伝統芸能・舞文化があるという。これらはすべて、地域ごとの伝説や独特の宗教観が生み出した架空の神様といえる。
獅子舞というと獅子頭に目が行くが、獅子幕こそが伝説の中での獅子の大きさや規模、地域性や畏敬の対象を表現したものではないかと調べてみると、やはり水災が多い地域は波しぶき、水玉は雨乞い、獅子毛は子孫繁栄・豊作祈願など、地域ごとに敬いの対象を獅子幕の柄に表現してきたようだ。(黒は水を表すなど、自然の色も幕の表現に使われる)。スコットランドのタータン柄が、伝承される地域や家督・氏族制度を表すように、テキスタイルで自らの地域性を表現することが遠く離れた日本でも行われてきたのである。獅子を演じる演者 たち(地域の若衆)たちは 〝演技〟が始まるまでは獅子頭に尻尾(獅子幕)をかませ、動き出す瞬間にそれまで平面だった布の中に入り、地域の平和と子孫繁栄を願う神として具現化する。獅子頭だけでは神様を演じるには足りず、布の中に人が入ることで大きな胴体となり、強い畏れの念を表現したのだろう。 彼らは架空の神様になりきって解放された喜び、恐ろしさ、荒々しさを表現する。
地域のお祭りとかお正月と言えば、父が駆り出されて青年団のみなさんと一緒に近所の神社で獅子舞を踊っていた。成長を願って頭を噛んでもらうようにと獅子の前に出される子どもは恐ろしくて泣いている。「怖い。おねがいだから近づかないで」。 大人たちは「ありがとさま」「おせわさま」だとか言いながら、その様子が可笑しくて笑っているが、子どもとしては全然安心していられない。物心つくまでは私も泣く側だったに違いないが、ちょっと大きくなってからは獅子の後ろで幕を持っているのは父だとわかっていたので、嬉し恥ずかし誇らしげな気持ちになった。でも獅子舞のメインはやっぱり獅子頭なので、なんでうちのお父さんは布を持っているんだろうと子どものころは思っていた。
今思うと獅子幕は変身マントのようだ。きっとどの地域のお父さんも、地域の発展を願い、子どもたちに泣かれながらも〝獅子〟に変身しているのだ。そう思うと、なんだかとてもほほえましい。
蜜蝋キャンドル:柴山修平
朝日町の森の中にある工房で、蜜蝋キャンドルをつくる養蜂家の安藤さん。なんと日本で初めての蜜蝋キャンドル工房です。
一匹のミツバチが、生涯で集められるハチミツの量は小さなスプーン一杯分といいます。数え切れないミツバチたちの労力によってできた蜜蝋キャンドルからは、ミツバチと森と、安藤さんのたくさんの愛情を感じます。
安藤さんは震災後、被災地へともしびを届ける活動「キャンドルリンク3・11」などの震災復興にも取り組んでいますが、やわらかく揺らめく灯りを見つめていると、真っ暗闇の中電気が使えなかったあの夜をふと思い出します。
道具には、「第一の道具と第二の道具」があると聞いたことがあります。ペンや食器などのいわゆる生活工芸のことを指す「第一の道具」に対し、「第二の道具」とは、「心への作用」がある道具。
安藤さんのキャンドルは、まさにそんな「心へ作用する」道具ではないでしょうか。震災以降、あらためて道具の意味を問い直すきっかけとなったのが、安藤さんの蜜蝋キャンドルでした。
編み南蛮:柴山修平
私の家の台所には、編み南蛮を壁に飾っています。唐辛子を藁で一列に編み上げたもので、ときどきそこから唐辛子を抜き取って料理に使っています。 赤い唐辛子を魔除けとして吊るす風習は、おそらく中国から伝わり山形の家庭でもよく見ることがあります。まさにそんな魔除けの風貌をした編み南蛮は、「魔除け」「保存」「実用性」と、三つの機能(魔除けは機能ではないが)を備えており、我が家の台所の神様になっています。
つくっているのは、真室川町で地域のお年寄りから藁編みの技術を受け継いだ高橋伸一さん。弥生時代より続く藁の文化を継承し、ワークショップやいまの暮らしにあった新しい藁の道具をつくり続けています。藁細工は、農耕文化の産物です。加工性の容易さや通気性のよさから梱包、保存、運搬に重宝され、稲作の副産物である藁に神の恩恵を重ね合わせることで、注連縄として神事にも使われてきました。
伸一さん自身も、真室川の伝承野菜の継承者である農家です。農家として地域に受け継がれてきた知恵や技術を、次世代に発信しようと奮闘しています。私も何度か習いに行っていますが… まだまだ習得するには時間がかかりそうです。
刃物:柴山修平
「刃物」という道具は、完成した瞬間に「力」を持つ不思議な道具です。自然界の木や獣、土に刃を入れる、打ち込むという行為は、人間が生きることそのものでもあり、刃物は自然との対話の道具として用いられてきたのではないかと思っています。古来の日本史では、刃物(剣)は三種の神器のひとつです。自然と対峙しながら使われることで、「畏敬が宿る」道具。それが刃物ではないでしょうか。
山形には、農業、林業、果樹、採集、狩猟、大工、家具屋、造園業など、刃物を必要とする多様な職業があります。各家庭の台所を見ても、菜切り包丁や三徳包丁など、多くの刃物があります。こんなに多様な刃物を使うのは、山形の暮らしが自然と隣り 合っているからではないでしょうか。
そこには、多様な職人に寄り添って「道具」をつくり続けてきた優秀な鍛治職人が欠かせません。よい鍛治職人がよい産業を育て、よい産業がよい鍛治職人を育てる。切磋琢磨しながら、山形の暮らしや産業を支えている山形の「道具」は、それぞれの方面で独自の進化を遂げています。
山形の打刃物は、今から約650年程前の室町時代(1350年頃)に、最上氏の始祖である当時の将軍が腕のいい鍛冶氏たちを率いて鍛治集落を形成し、武具や農具をつくり始めたのが起源と言われています。山形の鍛冶屋は、「農業」と共に発生して成長 してきたので、たとえば農作業で使うクワが進化して台所で使う三徳包丁になっていたり、そういう痕跡がモノにも現れているのでおもしろいんです。
山形で暮らしているとき、身の回りのものは友人や知り合いの「つくり手」につくってもらうことが多かったです。そんなつくり手が多かったのでしょう。例えばニットのマフラーは友人の恵君につくってもらおう、とか、こんな感じの器をあの人とつくれないだろうか、など。
あるときふと包丁が欲しくなったとき、刃物の職人は周りにいませんでした。そこで、麻の絨毯をつくってもらっていた穂積繊維の穂積さんに相談すると、知人の方を紹介してもらうことができました。それが、代々の鍛治職人である島田刃物の嶋田さんです。
ただ、そこからのコミュニケーションがなかなか難しくて、何度も訪ねたり電話をしたりしながら想いを伝え続けたんですが、なかなかつくってもらえるところまでいかない。諦めかけていたある日、ふと伺うと、つくると言ってもらえていなかったのに図面通りの試作品がいくつかできていたんです。嬉しかったですね。ああ、これが山形のつくり手だな、と感じたことを覚えています。